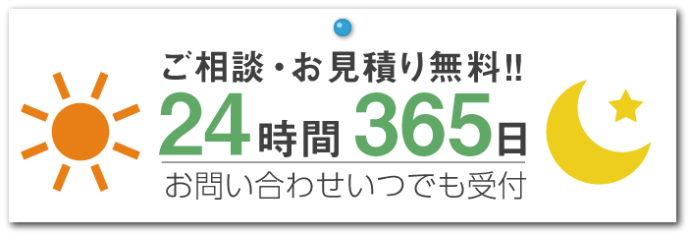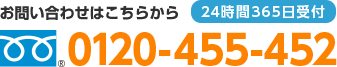イエコマの雨どい修理
※戸建て専門のため、集合住宅・ビル・店舗・工場などは受付不可となります

※サービスによって対応エリアが異なります。あらかじめ、各サービスページをご覧ください。
※戸建住宅向けのサービスとなっておりますので、集合住宅(アパート・マンション)、ビル、店舗、工場等の作業はお受けすることができません。
※作業は居住部分に限ります。
※借家の場合、大家様の許可および立ち合いが必須条件となります。
※現地調査が必要になります。
※生産中止品の部品は入手できない場合があります
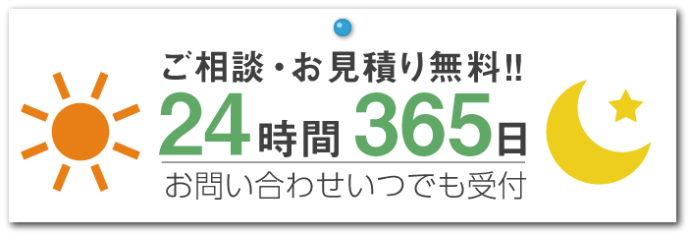
雨樋の破損・曲がりを放置するとどうなるか

雨樋は、少しくらい壊れていたり、雨水が雨樋から漏れていたりしても生活には直接支障がないので、すぐに対処する必要はないだろうと思う方もいるかもしれません。
しかし、雨樋が正常に機能しないと、以下のように家屋に重大な影響があるので注意が必要です。
- 大量の雨水が壁をつたい、外壁の寿命が縮まる
- 外壁からの雨漏りの原因となる
- 外壁から雨水が浸み込み、躯体を腐らせたりシロアリが発生することがある
- 雨水がモルタル壁などのクラックに侵入し、腐食を進行させる
- 地面がえぐれて基礎が露出し、建物自体の強度が保たれなくなる
- 大量の雨が屋根から落下するため、騒音の原因になる
>>『雨樋が破損する主な原因』に移動
>>『原因別の雨樋修理方法』に移動
イエコマの雨樋修理の特徴
業界最安値に挑戦する安値価格
作業地域・日程の最適化によって移動にかかる時間・コストを最低限に抑えました。
そのためお問い合わせをいただいてすぐにいけないことは多いのですが、最安値に近い価格でサービスを提供しています。
家を知りつくしているから安心
イエコマが提携する会社の家を知り尽くしたプロのスタッフがお伺いします。スタッフは家の構造を熟知し、安全、確実に、しかも安価に工事を実施します。
また、単に壊れている箇所を修理するだけではありません。
派遣されるスタッフは修理の過程において他の部分の不具合を見つけた場合、ベストな解決方法をご提案することができます。
雨樋の破損があるといったケースでは、同時に屋根の瓦のズレ、外壁の傷みなどが同時に発生していることが多々あります。
雨樋の破損は問題の一部分にすぎないかもしれません。
様々な解決策の中からベストのご提案をしますが、その提案をもとに他の工事業者に依頼していただいてももちろん構いません。
任せて安心イエコマにお気軽にご連絡ください。
>>イエコマは、雨どいクリーニングも提供しております。
10,780円(税込)追加料金一切なし!
>>イエコマは、雨どい落ち葉除けネット取付も提供しております。
10m以内 27,500円(税込)!
1m追加 +990円/m(税込)!※別途材料費かかります
雨樋の役割
軒のすぐ下に設置されている長いレール状の部品。これは何だろう?と気になった方もいるのではないでしょうか。
雨樋は、屋根に降った雨水を軒先で集め、スムーズに地下へと排水するための重要な設備です。
もし屋根に雨樋がついていなければ、雨水が直接外壁をつたい、外壁そのものを劣化させてしまったり、屋根から落ちた雨水で地面が掘り下げられたりと、さまざまな問題が起こります。
特に、雨水が集中的に地面に浸水すると、住宅を支える基礎部分を腐らせてしまうこともあり、とても危険です。
雨樋は、住宅の耐久性を守るためになくてはならない存在なのです。
雨樋のパーツ
雨樋は、主に以下のパーツから成り立っています。
<軒樋>
屋根の下にぐるっと回るように設置されているパーツです。屋根面からの雨水を受け、勾配をつけることで雨水を竪樋まで流します。
<竪樋>
軒樋から流れてきた雨水を、地面まで垂直に落とすパーツです。主に、住宅の角部分に取り付けられています。
<集水器>
軒樋から流れてきた雨水を集め、竪樋へとつなぐパーツです。
<支持金具>
軒樋や竪樋を建物に取り付け、固定するためのパーツです。
<止まり>
軒樋の端にある、雨水をせき止めるためのパーツです。
<継手>
軒樋同士をつなぐためのパーツです。
雨樋が破損する主な原因
1.落ち葉・ビニールなどのゴミが詰まる
立木が近くにあるような家では、枯れ葉による詰まりが発生しやすいです。
普段見えない箇所だけにトラブルになるまでわかりにくいのでやっかいです。
2.雨樋金具の劣化・雪の重みによる曲がり
雨樋金具が劣化して折れる、抜けるといったことは時折見られます。
また、積雪によって雪が雨樋にたまり重みで曲がったりすることはよくあります。
3.雨樋そのものの経年劣化
雨樋によく使われる材質は塩化ビニール・ガルバリウム鋼板・トタン・アルミ・ステンレスなどがあります。
塩化ビニールは軽くて安価、かつ切断加工が容易なため最も多く使われています。その反面、太陽から降り注ぐ紫外線の影響によって劣化しやすい欠点があります。最初はしなりによって衝撃を吸収するのですが、劣化によってしなるのではなく割れたり曲がりといったトラブルが起こるようになります。
トタンはさびると、すぐに雨漏りするようになります。 重みで一部が垂れ下がったりすると、そこに雨水がたまり、一気に腐食が進むようになります。
ガルバリウム鋼板など金属製の雨樋は塩化ビニールに比べると長寿命ではあり、さびにくい丈夫な素材です。 しかし他の金属と接していることで電食(異種金属接触腐食)という現象が発生し、さびてしまうことがあります。 これは建築業者の施工のレベルが低い場合にみられます。
4.雨樋の継手に隙間がある
接着不良や経年変化により、雨樋の継手部分が外れてしまうことがあります。
雨樋の継手部分に隙間ができると、雨水をうまく排水できずに、外壁や地面に雨水が直接浸み込んでしまう可能性があります。
5.強風による破損
台風や強風、風で飛ばされてきた飛来物が雨樋に衝突することによって、雨樋が変形したり破損したりすることがあります。
台風や強風の後は、雨樋のチェックを怠らないようにしましょう。
原因別の雨樋修理方法
ここでは、原因別に雨樋の修理方法を説明していきます。
屋根の上という高所での作業となるので、作業を行う時間帯や天候、サポートしてくれる人がいるかなど、安全面には十分注意しましょう。
もし少しでも不安に感じた場合は、専門の業者に依頼することをおすすめします。
ゴミの詰まりが原因の場合
雨樋には、ゴミが詰まりやすい3つの箇所「集水器」「軒樋」「竪樋」があり、これらを定期的に掃除することで、雨水の通りをよくすることができます。
〈必要な道具〉
- ハシゴ(屋根に上る際に使用します)
- ほうき もしくは トング(軒樋と集水器のゴミを取り除く際に使用します)
- ホース もしくは バケツ(ゴミの詰まり解消を確認する際に使用します)
- 長い針金、汚れても良い布 もしくは スポンジ(竪樋のゴミを取り除く際に使用します)
〈掃除方法〉
- 集水器のゴミ詰まり
- ハシゴを集水器付近に立てかけて上り、集水器に溜まっているゴミをトングで取り除きます。手作業で取り除きたい場合は、怪我をしないように必ず軍手をはめて作業をしましょう。
手前に溜まっているゴミだけでなく、少し奥の方までゴミがあるか確認し、水の流れを妨げる障害物を取り除いていきます。
最後に、ホースかバケツを用いて集水器に水を流し、スムーズに流れていれば掃除完了です。
- 軒樋のゴミ詰まり
- ハシゴを使って屋根に上り、軒樋の溝に溜まっているゴミをほうきやトングで取り除きます。
その後、ホースやバケツを用いて水を流し、水の流れを遮るものがないか、水が漏れている箇所はないかを確認します。水の流れに問題がなければ、作業終了です。
- 竪樋のゴミ詰まり
- 竪樋は、固定金具を外すことで下部の継ぎ目部分を取り外すことができます。
まずは、竪樋を取り外して中が見えるようにし、ゴミの取り除き作業を行っていきます。
竪樋より1メートル以上長く、比較的硬めの針金を準備し、汚れても良いボール状にした布もしくはスポンジを針金の先端にくくりつけます。
そしてハシゴに上り、布もしくはスポンジを取り付けた針金を竪樋の上部から中に差し込みます。針金を上下左右に動かして貫通させ、詰まっていたゴミを竪樋の下部から取り除きます。 この作業を2回程繰り返せば、ほとんどのゴミを取り除くことができます。
軒樋の傾斜が原因の場合
雨樋の軒樋には、わずかな傾斜がついており、屋根から落ちた雨水をスムーズに集水器・竪樋へと流す役割を果たしています。
軒樋の傾斜がなくなると雨水の流れが悪くなり、軒樋から雨水があふれ出て直接外壁をつたったり、地面に落ちたりしてしまうので、傾斜角を元に戻す必要があります。
〈必要な道具〉
〈対処方法〉
軒樋の傾斜は、軒樋自体についているものではなく、建物に取り付けられた支持金具により調整されています。
よって、軒樋の傾斜を調整したい場合は、ハシゴに上り直接手で支持金具を曲げて軒樋に角度をつけていくのです。
軒樋の傾斜は、大体10メートルにつき3~5センチメートル沈み込むような角度にします。
あまり力を入れすぎると支持金具が破損してしまう危険があるので、注意して行いましょう。
経年劣化が原因の場合
雨樋の寿命は、20~25年といわれています。長年使っていて、雨樋に穴が空いたり変形したりして水漏れがある場合は、経年変化だと考えられます。
〈対処方法〉
応急処置としては、コーキングや塗装を施すという方法もありますが、できるだけ早く雨樋を交換することをおすすめします。 なぜなら、雨樋全体の劣化が進行している限り、別の場所でも不具合が生じる可能性が高いからです。
雨樋全体を交換する場合は、1階部分だけでなく2階や3階部分も行うので、足場を組む必要があります。
自力で修理するのではなく、業者に依頼する方が正確かつ安全です。
雨樋の継手が外れている場合
雨樋の継手が外れてしまっている、または隙間から雨水が漏れている場合は、部材を交換することで修理が可能です。
ただし、同時に複数の継手部分が取れかかっている場合は、施工不良が原因とも考えられます。 この場合は、施工会社に再修理をしてもらうなどの方法もあります。
また、雨樋の寿命である20~25年が経過しているときは、経年変化による不具合とも考えられるので、全ての雨樋を交換したほうがよい場合もあります。
〈必要な道具〉
〈対処方法〉
ハシゴに上り、古い継手を取り外します。
次に、新しい継手を接着する部分(軒樋の端っこの部分)の汚れやホコリなどを十分にふき取ります。
最後に、新しい継手の接着面にしっかりと雨樋用接着剤を塗り、継手と軒樋を密着させて修理完了です。
風や雪などが原因の場合
台風や強風、豪雪などで、雨樋が破損することがあります。
たとえば、強風で軒樋の接着部分が外れたり、雪の重みで歪んだりするのです。
風や雪が原因の場合は一戸建ての最上階部分の雨樋が破損しやすく、高所での修理作業となります。 そのため、自分で修理するのではなく業者に依頼することをおすすめします。
また、火災保険に加入済みであれば、雨樋の修理交換工事費用を加入している火災保険で賄える可能性があるので、一度保険会社に確認するとよいでしょう。
もし、保険適用外で破損個所が高所(2階や3階の雨樋)でない場合は、破損した部材の交換を自分で行うのもよいでしょう。
軒樋を部分的に交換する方法を下記でお伝えします。
〈必要な道具〉
- ハシゴ
- 新しい軒樋
- 新しい継手
- 金切りノコ
- 雨樋用接着剤
〈対処方法〉
まずはハシゴに上り、古い軒樋を取り外します。 部分的に軒樋を取り外したい場合は、金切りノコで交換箇所を切断します。
次に、新しい軒樋を金切りノコで切り出します。取り外した軒樋を隣に置いて、同じ長さになるように新しい軒樋を切断するとやりやすいです。
そして、切り出した新しい軒樋を支持金具の上に乗せ、金具の前のツメを折り返し、しっかりと固定します。
最後に、雨樋用接着剤を新しい継手に十分につけ、新しく取り付ける軒樋の継ぎ目部分を補強します。接着が甘いと、継手の隙間から雨水が漏れてしまうので、しっかり固定するようにしましょう。
これで作業完了です。
雨樋修理の相場
雨樋の不具合を修理業者に直してもらう場合、相場は以下のようになります。
これはあくまで目安なので、依頼する際は必ず価格を確認してから契約しましょう。
- 雨樋の継手修理・・・・・・・4,000~25,000円/箇所
- 雨樋・支持金具の修理・・・・8,000~30,000円/箇所
- 雨樋の交換修理(一部)・・・10,000~40,000円/箇所
- 雨樋の交換修理(全体)・・・120,000~600,000円/全体
無料で雨樋の修理ができるって本当?
実は、場合によっては無料で雨樋の修理ができることをご存知でしょうか?
加入している火災保険で雨樋の修理をする方法を紹介します。
火災保険が適用できる場合
台風や強風、豪雪などにより雨樋が破損してしまった場合は、火災保険の「風災補償」「雪災補償」「ヒョウ災補償」を適用し、無料で雨樋の修理をすることができます。
「補償」とは、損害が生じたときに保険会社がその損害金額(修理費用)を賄ってくれることです。 つまり、火災保険に加入している場合は、風や雪により雨樋が破損したときに保険会社が修理費用を負担してくれるのです。
「風災補償」の条件
「雪災補償」や「ヒョウ災補償」は比較的理解しやすいですが、「風」は普段から吹いているものなので、「風災補償」がどのような条件で適用されるのか気になる方もいるのではないでしょうか。
台風や竜巻、暴風雨、突風、木枯らし、春一番など、強い風が吹くことはたくさんありますが、風災補償が適用されるのは、「最大瞬間風速20m/秒以上の風が吹くことによって生じた破損」と判断されています。
最大瞬間風速20m/秒以上の風が吹くのは、実はあまり珍しいことではありません。
強風により、または強風による飛来物が衝突したことにより、雨樋が破損してしまった場合は、風災補償が適用されると覚えておきましょう。
火災保険を申請する方法
火災保険を適用し屋根を修理するには、どのような工程を踏めばよいのでしょうか?
火災保険申請の手順と、それぞれの工程で抑えるべきポイントを下記に示していますので、申請の際はぜひ参考にしてみてください。
1、保険会社に連絡し、被災内容を伝える
加入している保険会社や保険代理店に雨樋の被災内容を報告し、保険申請の方法や必要書類について確認します。保険適用の被災内容であることをはっきり伝えることがポイントです。
2、申請書類を作成する
申請に必要な書類は、下記の4点です。
- 保険金請求書
- 事故状況説明書
- 修理見積書
- 被害物の写真
3、修理会社に「調査・見積書」の作成を依頼する
修理業者に連絡し、「調査・見積書」を作成してもらいます。
「調査・見積書」は、一般向けのものと保険会社提出用のものとでそれぞれ形式が異なるので、保険会社提出用の見積書作成経験がある業者に頼むのがよいでしょう。
ただし、書類を作成した時点で「契約」とする会社も存在するので、注意が必要です。
4、保険会社に現地調査を依頼する
保険会社または保険代理店が、保険鑑定会社の保険監査人を派遣し、現地調査を行います。
5、保険金を受け取る
保険会社から保険金確定の連絡が来ます。
現地調査を行ってから7~10日ほどで、見積内容に対する回答が得られるはずです。
もし書類作成が大変だと感じる場合は、「火災保険の申請代行サービス」も対応してくれる雨樋修理専門店か屋根修理業者 もあるので、相談してみるのもよいでしょう。
雨樋修理を依頼する業者の選び方
雨樋の修理を業者に依頼する場合は、どのような点に気をつければよいのでしょうか?
まず、依頼する修理の種類によって、業者を選択することをおすすめします。
雨樋の清掃作業を業者に依頼する場合は、便利屋ようなのところに依頼することをおすすめします。
なぜなら、雨樋の清掃作業は専門的な知識や技術が必要なわけではなく、比較的簡単にできるからです。丁寧で比較的安価に清掃してくれる業者もあるでしょう。
雨樋の交換作業を依頼する場合は、屋根の修理業者に依頼することをおすすめします。
高所で作業を行う場合は足場を組むこともあり、ある程度の専門的な技術が必要だからです。
業者に依頼するときは、まずホームページなどで業者の実績や口コミ情報を確認し、正確かつ丁寧に作業を行ってくれそうか確認しましょう。
そして、必ず数社から見積を出してもらい、適正価格を見極めます。
見積りを出してもらった時点で契約を急ぐような業者は、悪徳業者である可能性が高いです。困っていることに対して親切に答えてくれる業者を選ぶように心がけましょう。
雨樋の手入れ方法
住宅で長く快適に過ごすためには、日々のメンテナンスを怠らず、丁寧な暮らしを心がけることが大切です。
以下の点に注意しながら定期的に雨樋の点検・メンテナンスを行っていきましょう。
- ゴミが溜まっていないか
- 軒樋が歪んでいないか
- 継手が割れたり外れたりしていないか
- 支持金具が曲がっていないか
雨樋に不具合が生じるのは、経年変化、台風・強風・積雪などの天候的要因、施工不良などが原因です。
台風や強風の後や、季節の変わり目などに近隣の樹木から葉っぱや実が落ちるタイミングなどに、毎回点検やメンテナンスを心がけましょう。
また、雨樋にゴミが溜まっている場合は、ゴミの重みで軒樋の歪みを引き起こす場合もあるので、できるだけ早めに取り除くようにしましょう。