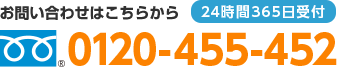施工事例
屋根の棟板金リフォーム施工事例

Before 釘の浮いているのが分かります。これが異音の原因でした。

After1 スクリュー釘で止めることによって、より強固に固定されました。

After2 スクリュー釘でしっかり押さえられ、もう異音はしなくなりました。
屋根の棟板金リフォーム施工事例
「釘を打つ」の教訓
「釘を打つ」の語源とその由来:あとで、問題が起きないよう、予め念を押すこと。
鎌倉時代まで建物に釘を使うことはなかった。木部にミゾを彫り、そこにホゾを埋めて繋ぎ合わせていた。釘が使われ始めたのは鎌倉時代。江戸時代の中期より、それを打つことによって、より木の接合を強める意味から、教訓的な意味となった。(GOO国語辞典)
静岡県I市のK様邸は、中堅住宅メーカーの注文住宅で建てられたものです。しかし、屋根だけは、施主様が別途頼まれた別の屋根業者の施工によるものでした。これを住宅業界では「施主支給」と呼んでいます。この施主支給を、たいがいの住宅メーカーは嫌がるのですが、受注を受けるために仕方なく
受け入れることも多いようです。問題は、ある部分の工事だけを、メーカーでない別の業者がやるものですから、他の工事個所との関係や兼ね合い、また現場監督の指揮や責任の範囲、さらに完成後のメーカー保証といった点で、いろいろと問題が起きやすくなっています。このK様の場合も、棟板金の釘打ちで問題が起きてしまったようです。
K様はある時、風が吹く度に屋根から異音が聴こえてくることに気付きました。数年はそのままにしておかれたのですが、やがてその音がだんだんと大きくなり、さすがに心配になってきたとのことで、今回、メンテナンスの依頼をいただきました。
そこで屋根に上って調べたところ、隅棟の板金が何枚か浮いていることが分かりました。平釘が打たれていたからです。
通常こうした屋根板金を打つ場合は、抜けやすい平釘でなく、たとえばスクリュー釘のような、その刀身の部分がネジ状となっていて抜けにくい種類の釘で打つことが常識です。それがなぜそうなってしまったのか今となっては分かりません。
幸いなことに修理自体はそんなに難しい事ではなく済みそうでした。浮いた屋根板金をいったん外し、あらためてスクリュー釘で打ち止めていくことで、元の正しい状態に戻すことが出来ます。

1

2
棟板金の釘が外され、いったん全部、棟カバーが取り外されました。板金を取り付けている桟木の貫板に水が染みた形跡はなく、大丈夫なようです(1)。
棟カバーは、ステンレス製のようです。裏側を見ると、ゴム製かポリウレタン製の防水パッキングが取り付けられており、雨水の浸入を防止する仕掛けとなっています。けっこうめずらしい高級品のようです。それだけに、平釘での抑えのあやまちは悔やまれるものとなりました(2)。

3

4
板金をコーキングで留めながら、新しく釘を打ちます。今度は、間違いなくスクリュー釘で押さえられていきます(3)。
釘打ちのあとで、コーキング材を充填して、棟カバーが順番に重ねられます。釘の頭にもコーキング材が充填されました。こうなるともう抜けることはありません(4)。

5
しっかりと棟板金が取り付けられました。もう音がすることはありません。
■ まとめ
棟板金の釘打ち施工は無事終わりました。「施主支給」という工事には、こうした弱点が見られることも多くあります。建物全体工事の統制がはかれにくくなり、監督、保証、メンテナンスの整合性が悪くなります。そして後々のトラブルの原因ともなります。なるべくであれば、一つの建築業者に任せましょう。
それにしても、「釘を打つ」の言葉の教えは、それが文字通りの場合には通用しませんでしたね。
釘を打つことは鎌倉時代から始まったようですが、時代は平成の御代となりました。そしてその御代も、すでに移り変わろうとしています。ですから、江戸時代の中期から長く言い継がれてきたその『釘を打つ』の言い方も、少し変わるかもしれません。今度は、その念を押すことの意味が、「スクリュー釘を打つ」に変わるかも知れないですね。

抜けない、錆びない、ステンレス製のスクリュー釘
画像出典:カナマル産業株式会社