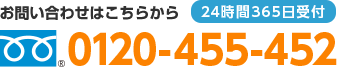施工事例
時代が要求する屋根の変遷-瓦屋根葺き替え施工事例

Before

before
Beforeの屋根。美しい甍(いらか)の波です。背後に見える山の借景と見事にマッチした美しい日本の屋根です。太陽光発電機が設置されています。

After
瓦に比べれば平板な屋根となりましたが、機能性は瓦に負けません。
時代が要求する屋根の変遷-瓦屋根葺き替え施工事例
日本で屋根瓦が用いられるようになってから千数百年に及びます。最初は名だたる寺院や仏閣、そして城郭建築や神社などに用いられてきました。それが民家にも多用されるようになったのは、江戸時代の中期頃のことです。良質の粘土で作られ、高熱で焼かれ、艶やかな色彩の上薬で仕上げられた日本瓦。その防水性と耐久性は50年から100年以上の耐用性を誇ります。
また瓦は、昔の日本建築の場合その土台が、土台石の上に置かれるだけで、今日の布基礎のようにそれが基礎に緊結されていませんでした。その建物を強風や烈風から守るために、その瓦の重量によって建物を重くすることで、より建物を安定させてきたのです。そのように日本瓦の活躍は、少なからず日本住宅の歴史において、欠くべからぬ役割を果たしてきたのでした。
そのように、昨今の住宅事情は、特に屋根に関しては、大分異なってきています。まず、強風による被害よりも、地震対策のほうに重きが置かれるようになりました。昔は、屋根を重くすることで、強風に耐えうる構造を作ってきたのですが、今から約20年前に起きた阪神淡路大震災により、屋根の重いことによって家の一階が押し潰される家が続出しました。さらに、基礎と土台は、その両者がボルトやナット、また基礎金具などによって緊結されることになり、強い風の影響による建物の安定性を心配する必要が無くなりました。このことから、屋根の重さを軽減させる必要が生じてきたのです。
またさらに、最近では屋根の上に太陽光発電器や温水器、またTVアンテナや天窓などを配置することが多くなってきています。したがって、童謡歌にも唄われた「いらかの波」も今では少しずつ姿を消しつつあります。しかし完全に無くなることはないでしょう。意匠的には、瓦屋根は日本の家屋や建物を代表する屋根です。そうした象徴的な役割を担って瓦の屋根はこれからも存続していくに違いありません。
今回ご紹介するS市のW様邸も、そんな時代の建物と言えるかもしれません。屋根の上に設置された太陽光発電機が原因となる瓦の損傷で、この度、屋根の葺き替えを実施されたのです。その結果をご覧いただきましょう。
問題の発覚
事の発端は、屋根裏への軽い雨漏りが発覚したことでした。原因を調査したところ、太陽光発電機を載せていた瓦の、架台装置の取り付け部分に不備が生じていることが発覚しました。
この原因の責任の所在については、一言断っておかなければならないかもしれません。この責任は、瓦業者に直接的な責任があるわけではありませんし、また太陽光発電機を設置した業者に直接的な責任があるわけでもありません。それぞれの仕事は、その時々において誠実にまた丁寧に施工されていた形跡が充分に伺えました。問題は日本瓦の持つ形状や特質またその取付方法が、本来この発電機の設置とはなじまず、配備の当初は大丈夫と思われたいたものが、やがてその後の経年劣化によって、つまり、自然の風雨や地震などに繰り返しさらされたことによって、徐々に不具合となっていったようです。
その原因としては、まず瓦の取付そのものに、ズレが生じやすいという傾向があります。特にそこへ何か重いものを載せると、余計にズレに繋がりやすいのです。また瓦の一枚一枚の形状が湾曲していることも、平板な架台の設置などには不向きです。
つまりそうした無理によって、架台の取付部分と瓦との接合点にすき間や穴などが生じて、次第に防水性を失っていった結果が、雨漏りの原因になったと判断されました。ではここでその修復工事の状況を見てまいりましょう。
太陽光発電機の撤去

1

2
一見、何事もないかのような美しい屋根の状況です。瓦そのものはまだ大丈夫です。

3
太陽光発電機を撤去したところです。結構大がかりな作業となりました。太陽光発電機が撤去された後の瓦を見ると、太陽光発電機の架台の取付箇所に不備が生じていました。それが雨漏りの原因となっていたようです。撤去後は新しい屋根材が取り付けられるまで養生されます。
葺き替え工事

4

5
瓦を取り除くと古い防水シートが現れました。多少、劣化しているようです(4)。
新しい合板の野地板が敷設されます(5)。

6
野地板の上に新しい防水シートが敷かれました。万一、屋根からの雨漏りが生じた場合でも、これが防いでくれます。

7
防水紙の上に太陽光発電機を設置するための位置付けが行われました。

8
架台にボルトが設置されました。屋根材が平板なため、取り付けに無理がありません。

9
太陽光発電機の架台が取り付けられました。屋根と架台との接合部分は防水のためのコーキングがしっかりと施されました。

10
配線が設置されました。

11
再び太陽光発電機が設置されました。

12
すべて終了しました。瓦屋根とはまた異なった機能美を有した屋根となりました
■ まとめ
このように近年では、屋根の上に様々なものを設置しなければならなくなった理由から、また地震対策といった観点からも、屋根を軽くした方が有利です。そのため、瓦中心だった日本の屋根も今日では少しずつその姿を変容させつつあります。瓦のように重くそして厚さのある屋根材から、洋瓦のような薄目で平板な瓦に変わったり、また軽い金属製の屋根材に変わったりしつつあるのです。
それにはまた、今の新しい家それ自体が、古来の和風的な家屋から、どちらかと言うと和洋折衷型や洋風建築に変わりつつある現状からも、そうした建物全体の意匠的な条件に要求されて、屋根材も少しずつ変わらざるを得ないのかも知れません。何事にも時代の変化は否めません。ただ確かに言えるのは、屋根材がどんなものであれ、屋根材のせいで家屋に自然災害が及ぶものであってはなりません。これからも丈夫で美しいものを求め、屋根の進化と進歩は飽くことなく続いていくことでしょう。