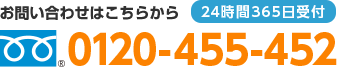施工事例
雨は時に、霧となって侵入するのです-下屋葺き替え施工事例

before

バルコニーの床を剥がして、雨漏りの原因を調べます。
写真は一階屋根とバルコニーです。一見したところ、屋根の上にバルコニーが乗っているわけですから、考え方によれば屋根が二重にあるようなもので、雨漏りには強いと思われますが、結果として現実は異なる結果となりました。雨は必ずしも上からまっすぐ降ってくる、しかも静かな雨ばかりだとは限りません。強風を伴う横殴りの風だってあるのです。するとそうした場合、屋根とバルコニー床下の狭い間に、強い風に煽られて風雨が凝縮されるように、より強烈な力となって入り込む、というよりは吹き込んでくるのです。そのように雨が吹き込んだ場合、屋根に少しでも欠陥があると雨はその欠陥を見逃してはくれません。そこにほんの少しの隙間やひび割れがあれば、また小さな穴からでも容赦なく、噴霧器の強圧で吹き付けるのと同じ原理で、建物内に霧となって吹き込んでくる結果となります。その結果雨漏りとなるのです。

after
作業途中で汚れて見えますが、新しい屋根が葺かれました。
この後きれいに掃除をしてバルコニーを載せれば完了です。
雨は時に、霧となって侵入するのです-下屋葺き替え施工事例
屋根の雨漏りは大屋根(2階部分に葺かれる、メインとなる屋根)だけとは限りません。一階の屋根から雨水が漏れる事だって珍しくありません。この度のS市のO様邸では、何とそのようにバルコニーが設置されている一階の屋根(下屋)から、その下内部のリビングルームへの雨漏りが見られたのです。
ところが雨が降ったその都度に漏れたかというと、そうではありません。年に10回くらいの雨漏りがあるらしいのですが、そのたいがいは南からの強い風が吹いているときか、もしくは台風の強い風雨の時に限られていたのです。
不思議でした。そこでO様から屋根の点検と葺き替えを依頼いただきました。まずはバルコニーをいったん撤去し、その原因を調べた後に、屋根の葺き替えも行われることとなったのです。
雨漏りの原因と屋根の葺き替え

1

2
まず、バルコニーの床が外されていきます。

3
いったんバルコニーは撤去されました。元の屋根は金属製の瓦棒葺きです。古くはなっていましたが、防水性はありました。それ自体が雨漏りの原因ではなかったようです。

4
雨漏れの原因がつかめました。屋根の奥と立ち上がり壁の接合部分をご覧ください。少しの隙間が見えていますが、バルコニー自体の重みやそこに乗る人の重量で屋根材自体が下がって隙間が生じたのかも知れません。検証の結果、その部分から雨の侵入があったことが分かりました。それでも普通の雨だったら漏れなかったかも知れません。でもバルコニー床下の狭いすき間から圧縮されて吹き込んでくる風雨にはかなわなかったようです。さらにその隙間から建物内には、噴霧器で吹き付けるような霧状の雨が吹き込んでいたに違いありません。

5
これを機会にO様は、屋根を新しいものに葺き替えられることとなりました。そして雨漏れの原因となった壁との部分には、しっかりと防水のためのコーキングが施されました。そして再度、実験の結果、雨漏りの心配はなくなりました。
バルコニー再設置

6

7

8
バルコニーが元通りに設置され、工事は終了しました。

9
雨漏りの心配のない屋根とバルコニーになりました。
■ まとめ
O様邸のバルコニーは、横幅の広いバルコニーですが、奥行きは比較的狭い半間(約0.9m)となっています。この場合、奥行きが一間(約1.8m)ほどあるなら、多いに事情は異なってきます。吹き付けた強烈な雨がバルコニーの床下にもぐり込んだ場合でも、奥行きがあることによって、雨の吹込む力が多少、緩和されるからです。またそうして奥行きがあるバルコニーの上に、さらにバルコニー用の屋根が付いていれば、より雨の侵入を防ぐことができます。そのような場合であれば、仮に今回の事例のように屋根に少し隙間があったとしても、雨漏りまで至るようなことはないでしょう。
雨の侵入は油断できません。雨は思ったよりも容易に、建物の中に入ってきます。時には強風による、より侵入しやすい噴霧状態で建物の中に深く入りこむ場合もあるのです。まるでSF映画に出てくる得体の知れないお化けのように、住人に気づかれないうちに侵略してきます。
その事をご説明申し上げたところ、O様の奥様が、ご主人にバルコニーの屋根を付けてほしいとお願いをされたようです。奥様も共働きで、洗濯物を干したまま職場に出勤されることが多く、お天気が悪くなってくると、働いていても気が気ではないとのこと。そういえば、先ほどバルコニーの床が外された時に、たくさんの洗濯バサミが落ちたままとなっていました。職場に行く前のあわてての洗濯干し、きっと毎日がお忙しいのでしょうね。