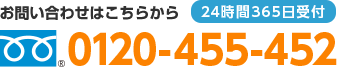施工事例
S様邸瓦の部分補修工事

Before 白いものは、割れた瓦を印すテープです

Before

After 部分的な補修を行いました。

Before 棟瓦も一枚、ひび割れが見つかりました。

After ビスを留め直してコーキングを施しました
■S様邸瓦の部分補修工事
茨城県にあるS様邸の事例をご紹介します。
実は最初にS様邸の屋根の異変を知ることが出来たのは、S様ご自身ではなく、隣家の方でした。
何事につけ案外に自分のことは自分では分からないものです。例えば、ある時会社で、いきなり自分の頭について、同僚や先輩から、「最近ちょっと薄くなったんじゃない」などと指摘されて、ショックを受ける、そのようなことと似ています。もし仮に、普段から、自分の後ろ頭を合わせ鏡で見ていても、自身では気が付かないか、あるいは少しひいき目に見て、自らをごまかしてしまうかもしれません。物事の真性は、事実を客観的に、また冷徹に観て初めて、悟ることができるのでしょう。
家もそれと同じです。誰もが自分の家だけはと信じたくて、そして屋根のように見たくても見えない部分があるとなおさら、疑うことを避けるか、あるいは面倒くささでついついごまかしてしまうものなのです。
S様の隣に住むR様は洗濯物を二階のバルコニーに干すので、そこから見えるS様邸の屋根の異変に、気付いたそうです。そのことを聞いたS様、さっそく調査の依頼をすることにしたそうです。そうしたところ、実に4枚もの瓦が割れており、また棟瓦の一枚にも破損もあることを知ることとなりました。

1

2

3 割れた瓦を取り外しました。雨漏りの心配はなさそうです。
このS様邸は築後約20年になります。確かに中古住宅ですが、それほど古くはありません。屋根瓦はセメント製の瓦で、結構丈夫な素材となっています。その厚さも薄くはありませんので、何事もなければ20年は裕に持ちますし、40年以上は耐用するとされている代物です。S様は小首をかしげて考えましたが思い当たるフシはありません。新築以来、S様も他の誰も屋根に上った記憶はありませんので、人為的とは考えられません。それでは何が原因だったのでしょうか。
一般的に、屋根が割れる原因は次のようなことがあげられます。
- 瓦そのもの耐用年数が尽きていること。その古さによって自然に割れること。
- 瓦そのものの最初からの欠陥(取り付けた時は新品でも直後に割れてしまう)。
- 人が乗ることによって割れること。例えば、家主、瓦業者、テレビのアンテナの取り付け等。
- 上空からの物の落下によるもの。飛行機からの氷や部品。または強風あおられた落下物の衝突。
- 雷の落雷による場合。(同時に複数枚、割れることが多い)。
- 地震、台風、雹等の天災地変や自然災害、あるいは悪天候によるもの。
- もしくは、上記の複合的な原因によるもの。総体的にはこの要因が多い。
S様邸の場合、古いスレート瓦ではあるものの、本来は丈夫なセメント製であるので、素材の悪さや耐用年数が尽きた要因とは考えられません。また人為的な原因や、落下物の形跡も見られませんでした。そうしたことから、地震の揺れによる衝撃波で割れてしまったのではないかと推測されます。
ただし、直接的には地震によるものとはいえ、20年という長い歳月による自然劣化や、また厳しい暑さ寒さの自然現象による劣化も大きく、そうしたところへ、地震の揺れという直接的な力が加えられて、割れた可能性が高いと考えられます。特に地震の場合、その揺れの衝撃波は、緻密に組まれた瓦同士のそれらが、相互に押し合いへし合う力関係となり、結果として、その中でも特に劣化の激しいそのうちの何枚かが、そうした衝撃波の集中的な破壊力を受け、犠牲となって割れることは多いのです。
その説明を聞いた時、ふとS様の脳裏によみがえったのが、数年前に起きたあの東日本大震災の記憶でした。S様の家は、関東でもその震源地に極めて近い処で、震度6弱の強震が観測され、倒壊した家屋はなかったものの多くの家の屋根が損壊を受けて、その後もしばらくは屋根にブルーシートが架けられていたという状況だったのです。さいわいS様のご自宅には、目視の範囲内での被害はなかったものですから、安心しておられたのでした。ところが、目立った被害はなかったものの、実際には目には見えないところでの小さな損傷を受けていたらしいのでした。
割れた瓦をはぐってみると、幸い雨漏りの形跡は殆んど無いようでした。仮にあったとしても、
その瓦の下に敷かれている防水紙のルーフィングで守られていたに違いありません。念のため屋根裏に潜って点検したのですが、それらしい形跡はありませんでした。そのため、割れた何枚かの瓦を取り除き、同じ種類の新しい瓦を入れることにしました。
ところがちょっと困った事となりました。というのは、実はそのスレート瓦がもうすでに廃版となっていたのです。そこで、倉庫に残っていたスレート瓦で対応することになりました。

4

5 新しい瓦を入れていきます。

6

7
棟瓦が浮いている箇所も見つかりました(6)。
棟瓦と棟瓦の間にすき間ができており、ビスが浮き上がっています。
この場合は、まずビスを外します(7)。

8

9
新しいビスで押さえてゆきます。その上にコーキングが施されます(8)。
破損した棟瓦は取り替えられ、はずれていた棟瓦は元の位置に納められて、しっかりとビス止めされて、棟瓦の連結部と、そしてビスの頭にはしっかりとコーキングが施されました(9)。

10 なんと綺麗な仕上がりでしょう。
屋根の修理は早期発見が鍵!とにかく点検は大切です
ところで、屋根の点検は、自分の頭が自分では見えないのと同じように、非常に難しいものです。
点検のポイントをまとめましたので、屋根の点検を検討されている方は、参考になさってみてください。
- 自分自身が直接、ハシゴをかけて屋根に上り、点検する。
- ただし、これは慣れなくて危険なこともでもあり、またハシゴがない場合も多いので、その場合は遠慮なく業者に依頼しましょう。
※イエコマでは点検だけでも無料で承っています。
- ベランダなど、見やすい場所から目視します。
- 100円ショップで売っているような簡単な双眼鏡があれば、より明確にまた確実に把握できます。
- 屋根裏(小屋裏)へ、雨の日かもしくはその直後に入ってみて、雨漏りがあるかどうか確認する。
- 実際に雨漏りしているか、あるいは雨水が漏れた形跡を示すシミがあるかないかを確認する
- ドローンを使っての空撮による点検。
- もしドローンがあれば、飛ばして異常がないか確認できます。ただし、人口集中地区の場合、ドローンの使用許可が必要なため注意しましょう。
屋根の異常は、なかなか気づきにくいものです。大体屋根は5~10年に一度はメンテナンスが必要です。
無理に屋根に上ろうとせず、5年くらいを目安に業者に点検を依頼されることをおすすめします。
イエコマでも無料で現地調査を行っていますので、お気軽にご連絡ください。

11 割れたところに、瓦が取り付けられました。

12
このようにして無事、瓦の取り換えは終了しました。新規の瓦は色が白いのでちょっと気にはなりますが、別途、塗装をすれば問題ないでしょう。
■ まとめ
ところで、もう少しで還暦を迎えようとされているS様、今回のこのことが影響してかどうかは分かりませんが、最近、やたらと自分の頭のことを気にし始められました。
そこで何度か奥様にそのことの客観性を求めて尋ねられたS様。すると奥様は、普段ほとんど見たことはないご主人の頭をあらためてしげしげと眺め、くすっと笑いをかみ殺すような仕草で口元を押さえて、視線を外しながら、「齢、相応でしょう」との極めてクールな返事。
それにしても屋根であれ自分の頭であれ、自分のことって、分からないですよね。本当に。