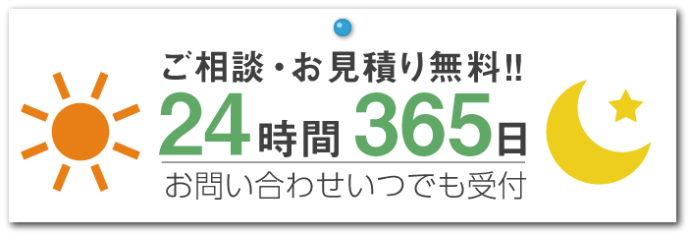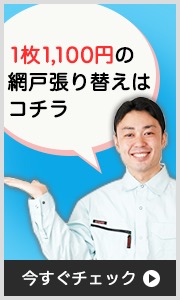「冬になると窓が結露でビショビショ。いつの間にか窓にカビが生えている!」
「窓のカビはどう対処したらいいのかな」
窓の結露が原因でカビが発生することに悩む人は少なくありません。
しかし、室内と外の温度差が大きい時に生じる結露は、避けられない現象です。
そこで本記事では、カビの掃除方法とカビの発生を抑える方法を解説します。窓の結露によるカビにお悩みの人は、ぜひ参考にしてください。
カビが発生する仕組み
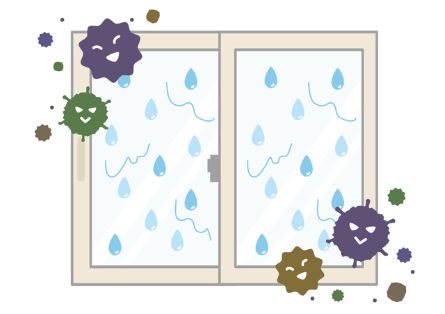
窓の結露でカビが発生する原因は、おもに水分と汚れです。
そもそも結露とは、室内の暖かい空気が冷たい窓ガラスに触れることで起こります。暖かい空気は水分を多く含んでおり、冷たい窓ガラスに触れることで冷やされます。空気に含まれる水分が水滴となってガラスに現れる現象が結露です。
とくに冬場は外気温の低下で窓ガラスが冷え、室内の暖かい空気が触れることで結露が発生しやすくなります。
カビは湿度が60%以上で発生しやすいです。結露で窓に水分がたまるとカビが発生し、窓の汚れを栄養源としてカビが繁殖しやすくなります。
窓の結露は、カビが発生する条件を満たしているのです。
窓のカビを放置するとどうなる
窓のカビを見つけたらすぐに対処することが肝心です。窓のカビを放置すると次のような悪影響が起こります。
- 人体への健康被害
- 他の場所にカビが広がる
健康被害

カビは、人間の体に悪い影響を与えます。カビを放置すると、カビの胞子が増殖し、空気中に浮遊します。部屋中に舞ったカビを吸い込むことで、アレルギーや喘息の症状を引き起こすのです。
カビが人体に与える影響は、おもに次のようなものです。
- くしゃみ・鼻水・咳などの呼吸器系症状
- 頭痛・めまい・倦怠感などシックハウス症候群
- かゆみ・湿疹など皮膚症状
カビは、呼吸器系やアレルギーに関わる問題を引き起こしやすいため、早期の対処が重要です。
他の場所に広がる

カビは一度発生すると、他の場所に広がるおそれがあります。カビの胞子が空中に舞い、部屋中に広がるからです。
たとえば、カーテン・壁・巾木(はばき※)・フローリング・天井などに、カビは繁殖します。部屋中にカビが広がると健康被害はもちろんのこと、家の劣化にも影響を及ぼします。カビが他の場所に広がる前に対策が必要です。
※巾木…壁と床の境目に取り付ける部材
カビの掃除方法
窓のカビの掃除方法を、初期・中期・後期とカビの進行具合別で解説します。
なお、カビ掃除は原則として、天気のよい日に行いましょう。晴れた日は、湿気が少なく換気ができるため、カビ掃除に適しています。
カビ掃除をするときは、次の準備をすることが大切です。
- 窓を開けて十分換気する
- カビを吸い込まないようにマスクをする
- 手が荒れないようにゴム手袋をする
- 目を保護するためにゴーグルをつける
カビ初期段階
カビの初期段階とは、少しのカビが見え始めた頃です。
カビの初期段階では、中性洗剤を使用してカビを落とせます。中性洗剤は、食器用洗剤などが使えます。
中性洗剤を使用した掃除方法は、次のとおりです。
- 1. 水に食器用洗剤をまぜる(水500mlに対し中性洗剤3~5ml)
- 2. 中性洗剤液を窓に直接スプレーし、5分ほど放置する
- 3. 汚れをふき取る
中性洗剤の成分がカビの胞子内に染み込み、カビを落としやすくします。
カビ中期段階
カビの中期段階とは、カビの範囲が広がり、目に見える量が増えてきている状況です。中性洗剤で落とせない場合は、酸素系漂白剤を使用して、カビ掃除をしましょう。
酸素系漂白剤は、窓枠や塗装部など素材を傷めにくく、比較的安全に使用できます。酸素系漂白剤の成分は、過炭酸ナトリウムであり、ワイドハイターやオキシクリーンなど衣類漂白剤が代表的です。
酸素系漂白剤を使用する掃除方法は、次のとおりです。
- 1. 酸素系漂白剤と水をあわせ、酸素系漂白剤液を作る(一般的に水1Lに対して約10g)
- 2. 酸素系漂白剤液をスプレーで吹きかけるか、スポンジなどで塗布し、10分放置する
- 3. 柔らかいスポンジや布でふき取る
カビ掃除後は、乾拭きをするなど乾燥させることが大切です。
カビ後期段階
カビ後期段階とは、カビが広範囲にわたって繁殖している状態です。カビの繁殖がひどい場合は、塩素系漂白剤や塩素系カビ取り剤を使用しましょう。
塩素系漂白剤の主成分は、次亜塩素酸ナトリウムです。代表的なものに台所用漂白剤であるキッチンハイターやブリーチなどがあります。また、カビ取り剤であるカビキラーなども塩素系で高い除菌力があります。
キッチンハイターなどの塩素系漂白剤は、水で10倍に薄めて使います。
塩素系漂白剤を使用する掃除方法は、次のとおりです。
- 1. 水で薄めた塩素系漂白剤またはカビ取り剤をカビ部分に吹きかける
(キッチンペーパーに薬液を染み込ませ、ラップで密閉すると効果的) - 2. 20分ほど放置する
- 3. ぬれ布巾でふき取る
塩素系の薬液は臭いがきつく、刺激が強いので、十分な換気とマスクや手袋の着用が大切です。
また、塩素系漂白剤がカーテンや木材などに付着すると、変色や傷みにつながります。塩素系漂白剤を使用する際には、注意しましょう。
カビの発生を抑える方法

カビの発生を抑えるには、以下の4つを行いましょう。
- 結露をふき取る
- こまめに換気する
- 部屋を除菌する
- カーテンを開ける
結露をふき取る
まずは、カビが発生する原因の1つである結露をふき取りましょう。窓の結露の発生自体を防ぐのは難しいため、冬場や梅雨の時期など結露が発生しやすい時期には、こまめにふくことが重要です。
窓をふく際には、下から上に向かってふくようにすることがポイントです。下から上にふくことで、サッシや窓枠に水がたまりにくくなり、カビの発生を抑えられます。
また、次のようなアイテムで、結露の発生を抑える対策があります。
- 結露防止スプレー
- 結露吸水テープ
- 結露防止シート
結露防止スプレーは窓にスプレーし、乾拭きすることで結露を防止します。
結露吸水テープは窓の下に貼るタイプの吸水テープです。結露が窓サッシにたまるのを防ぎます。
結露防止シートは、直接窓に張りつけて結露を防止します。
結露の発生を抑えたり、結露をこまめにふき取ったりすることが、カビの発生を防ぐことに有効です。
こまめに換気する
カビ対策では、こまめに換気することが大切です。カビは湿度60%以上になると発生しやすく、80%以上で繁殖しやすくなります。
部屋の空気を入れ替えることで、室内の余分な水蒸気を外へ逃がし、湿度を下げられます。換気は晴れた日に行うことが効果的です。
また、換気をすることで部屋の温度調節につながります。屋外との温度差が大きいと結露が発生しやすくなるので、部屋の温度調節も重要です。
部屋の除湿をする

カビを発生させないためには、部屋の除湿を行い、湿度を上げないことが重要です。前述したように、カビは湿度が高くなればなるほど発生し、繁殖しやすくなります。
部屋の湿度を下げるために、換気とセットで除湿器を併用すると効果的です。
除湿器がない場合は、エアコンの除湿機能を使ったり、除湿剤を使ったりすることも有効です。
カーテンを開ける

窓に結露が発生するときには、カーテンを開けるようにしましょう。
窓がぬれた状態でカーテンを閉めっぱなしにしていると、水分がカーテンに付着してカビが繁殖しやすくなります。
カーテンを開けて、結露がつかないようにしたり、カーテンにアルコール除菌スプレーを吹きかけたりすることも、カビの発生を抑えられます。
カビが繁殖しやすい環境を作らないように注意することが大切です。
まとめ
窓の結露を放っておくことは、カビの発生・繁殖の原因となります。
カビを放置しておくことは、人体に悪影響を及ぼし危険です。アレルギー反応や呼吸器系の疾患を悪化させるおそれがあるので、カビを発生・繁殖させない対応が重要です。
カビの発生を抑えるためには、結露をふき取ったり、換気をしたりしましょう。
また、カビが発生したら、繁殖させないように掃除をすることが大切です。
2重サッシの設置ならイエコマ



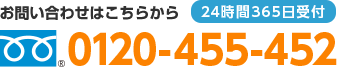

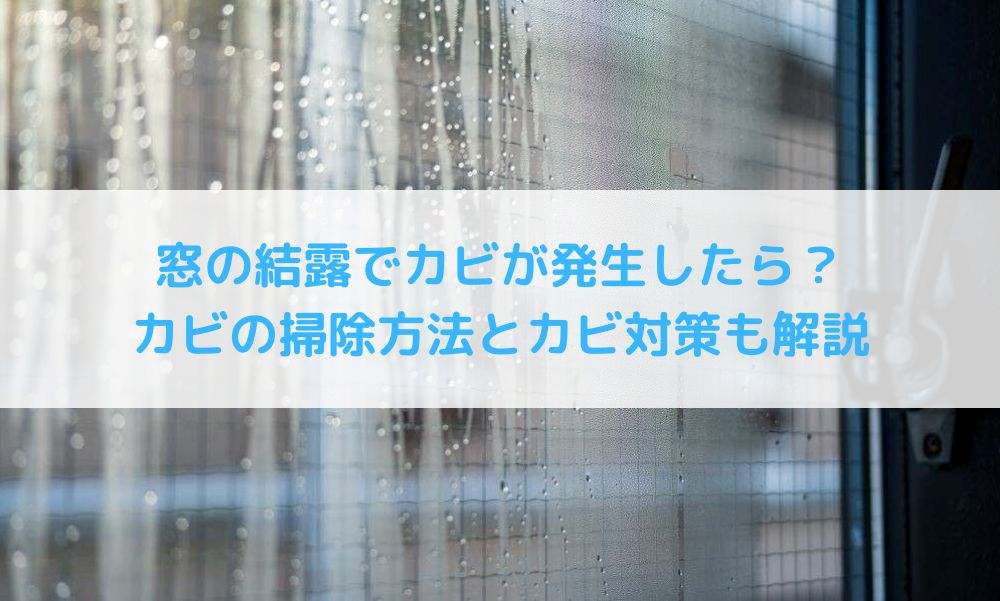
 寒さ・騒音とはおさらば!窓を換えて、快適な住まいを手に入れよう!
寒さ・騒音とはおさらば!窓を換えて、快適な住まいを手に入れよう!