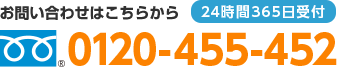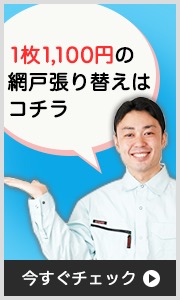住宅は、築年数が経つにつれて、さまざまな部分が劣化していきます。
劣化の程度や原因は、住宅の構造や材質、環境などによって異なりますが、長く住み続けるには定期的な点検・メンテナンスが不可欠です。住宅の劣化は、見た目や快適性だけでなく、安全性や耐震性にも影響する重要な問題です。
目に見える範囲は大丈夫そうでも、隠れたところで劣化が進んでいることもあります。
この記事では、築年数ごとの住宅の劣化状況の目安を解説し、長くお家に住み続けるためのコツを紹介します。
【築年数別】住宅の劣化の傾向
築年数ごとの、住宅の劣化の状況の傾向や工事の目安などをお伝えします。
築10年以内

築10年以内の住宅は、一般的にはまだ新しく、とくに大きな劣化は見られないことが多いです。
ただし、環境によっては築10年ほどでも劣化が目立ってくることもあります。たとえば、海沿いの地域のため塩害の影響を受けている場合などです。
経年劣化であってもなくても、家のどこかに不具合が発生している恐れはあるので、10年を目安に一度業者に点検してもらうのもよいでしょう。
住宅の引き渡しから10年以内で不具合が見つかったなら、まずは保証の範囲内で建築会社に対応してもらえるかどうか確認するのがおすすめです。
新築住宅は、引き渡しから10年の間に何か欠陥が見つかった場合、建築会社が責任を負うよう定められています。
ただし、保証で対応してもらえるのは、あくまで建築会社の不手際が原因で住宅に欠陥があった場合のみです。
築10~20年

築10~20年の住宅は劣化が目立ち始める時期です。とくに15年以上経つと劣化が目立つ傾向にあり、リフォーム時期の目安ともいわれています。
劣化の例としては、内装の床やクロス(壁紙)の傷み、窓やドアの開閉不良、浴室やキッチンなど水回りのカビや水漏れ、外壁の黒ずみやひび割れなどが挙げられます。
これらの劣化は、住み心地に悪影響を及ぼします。窓やドアの開け閉めがしづらいとストレスですし、マイホームに黒ずみやひび割れがあったら気になりますよね。
また、これらの劣化した箇所を5年や10年など長期間放置していると、後々の修繕費がかさむ恐れもあります。
そのため、築10~20年の住宅では、必要に応じて部分的な補修や改修を行うことが必要です。
築20~30年

築20~30年の住宅は、建物各所の劣化が本格的に進んできます。戸建て住宅は築30年前後で建て替えられることが多いので、その意味では寿命が近づいてくる時期といえるでしょう。
とくにこれといったリフォームを一切していない場合、屋根や外壁の雨漏り、断熱性や防音性の低下、水回りや配線の不具合などが出てくる恐れがあります。
ただし、注意すべき点が2点あります。
ひとつめは、30年前後の築年数になったからといって、暮らしに問題が出るほど住宅が劣化しているとは限らないことです。
戸建て住宅は築30年前後で建て替えられることが多いですが、築40年や50年で居住用に使われている場合もあります。
「築30年くらいで絶対に建て替えなきゃ」と考える必要はありません。
ふたつめは、住宅の状態は諸条件によって異なることです。
住宅の造り、これまでのリフォーム歴、メンテナンス状況、普段からの各種設備の使い方、立地などによって、同じ年数でも住宅の状態は変わってきます。
築年数は重要な目安のひとつですが、それだけにとらわれてはいけません。専門の業者に住宅の現在の状態をチェックしてもらい、このまま住み続けるのか、リフォームするのか建て替えるのか、検討しましょう。
長くお家に住み続けるコツとは
住宅の劣化のスピードや寿命は、さまざまな要因によって変わってきます。
住宅をできるだけ長く良い状態で保つためのコツは以下です。
定期的なメンテナンス

家に長く住み続けるためには、定期的なメンテナンスが重要です。
メンテナンスの具体的な例としては、次のようなものがあります。
- 住宅の構造(柱など建物を支える部分)の点検・補修
- 外壁や屋根の点検・補修・塗装
- 床の補修やクロス交換
- 水栓など各種設備の部品交換、あるいは設備自体の交換
上記のようなメンテナンスを定期的に実施することで、住み心地を維持したり、傷みの範囲が広がるのを防いだりすることができます。
メンテナンスは、基本的に専門の業者に依頼するのがおすすめです。メンテナンス作業は、高所作業を伴うものや専門知識を要するもの、正確にキレイに仕上げるためには経験が必要なものが多いです。
ドアや窓の建て付け調整のように、ドライバーがあれば自分でも実施しやすいメンテナンスもありますが、個々人の力量(手先の器用さなど)に左右される点に注意が必要です。
10年ごとに業者に点検とメンテナンスをしてもらいつつ、何か気になることがあれば業者に相談するのがよいでしょう。
自分で日々掃除を行う

住宅を良好な状態に保つには、日々の掃除も大切です。
掃除をすることで、床など家の各所の黒ずみを防いだり、水気によって木部が傷むのを防いだりすることができます。
理想の掃除頻度は毎日ですが、仕事やそのほかの用事などで難しければ、週に1度以上を目安にしましょう。
住宅で劣化しやすい場所とは
住宅の造りや立地、メンテナンス頻度などによって異なりますが、一般的には屋根、外壁、床、水回りなどが劣化しやすい場所と言えます。
これらの部分が劣化すると、住宅の快適性はもちろん、耐震性や耐火性などにも影響する恐れがあります。そのため、定期的に点検や補修を行うことが重要です。
屋根

屋根は雨風や日光などにさらされるため、劣化しやすい部分です。
屋根材の種類によりますが、屋根の劣化は、屋根材のひび割れや脱落、クギの浮き上がり、棟や谷のずれなどの形で現れます。
屋根の劣化が進むと、雨漏りや結露、断熱性の低下などの問題が発生する恐れがあります。また、台風などで屋根材が飛散すると、近くの住宅に損害を与えたり、通行人にけがをさせたりする恐れもあります。
屋根の点検の頻度は、3~5年に一度が望ましいです。難しい場合は、10年に一度を目安にするとよいでしょう。とくに台風や大雪などの災害後は注意深く確認する必要があります。
外壁

外壁も屋根と同様に風雨や紫外線にさらされるため、劣化しやすい部分です。
外壁の劣化は、塗装の剥がれや色あせ、黒ずみやひび割れ、カビや藻などの汚れなどの形で現れます。
外壁の劣化が進むと、外観を損なうだけでなく、断熱性や防音性の低下、建物内部への水分侵入などの問題が発生する恐れもあります。
外壁の点検は10年に1回程度行うことが望ましいです。
床

床は日常的に歩行や家具の移動などによる摩耗や衝撃を受けるため、劣化しやすい部分です。床の劣化は、床材のへこみや、沈みや浮き、ひどい床鳴りやきしみなどの形で現れます。
床の劣化が進むと、歩行時の不快感や危険性だけでなく、床下への水の侵入や害虫発生などの問題が発生する恐れがあります。
床の沈みや浮きが見られたら、早めに業者に相談しましょう。これらは、床下の土台部分の傷みやシロアリ被害の表れのこともあります。
床鳴りやきしみは、放っておいてもとくに問題ない場合もありますが、ひどい場合は業者に相談しましょう。
水回り

キッチンや浴室、トイレなどの水回りは、10~15年程度のスパンで設備の交換などの対処が必要な箇所です。
たとえば、水栓の耐久年数は10年程度といわれており、10年を超えると水漏れなどの問題が発生する恐れが高まってきます。
このため、設備の部品の交換、あるいは設備丸ごとの交換が必要になることがあるのです。
水回りの点検は10年に一度行うことが望ましいです。
また、水回りを使っていて、「もしかして水漏れしている?」「何か変?」と思ったら、業者に相談しましょう。異常を早期発見・対処することで、大きな被害を防ぐことができます。
まとめ
住宅は、築年数によって異なる劣化状況に直面しますが、定期的な点検やメンテナンスを行うことで、長く快適に住み続けることができます。
築10年を過ぎたら、住宅の各部分の点検を業者にしてもらい、住宅の状態に応じて必要な工事をしてもらうことが重要です。
住宅で主に劣化しやすい場所は、屋根・外壁・床・水回りです。これらの場所にはとくに注意を払いましょう。
住宅の劣化は、見た目だけでなく、住宅の機能や安全性にも影響しますので、早めに対処することが大切です。