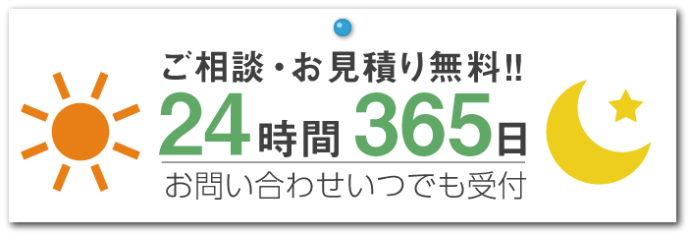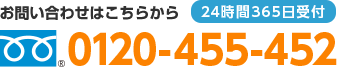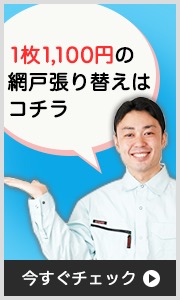「掃除はしているのに家の中が何となく臭い」と気になることはありませんか?
その臭いの原因はカビかもしれません。カビの臭いは、家の中のどこかでカビが増殖しているサインです。
健康や家屋にも悪影響を及ぼすカビの臭いに気付いたら、早めに対処しましょう。
この記事では、カビが発生しやすい場所やカビの原因、カビが生えた時の対処法などを紹介します。
「我が家の嫌な臭いはカビの臭い?」と悩んでいる人は、ぜひ参考にしてください。
目次
「カビ臭」とはどんな臭い?何が原因?
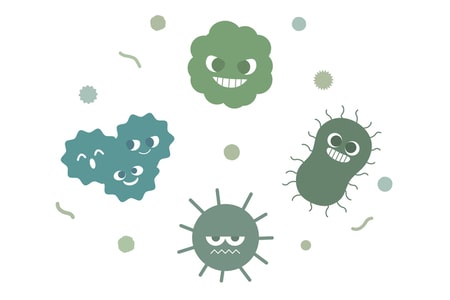
そもそも「カビ臭」とはどんな臭いでしょうか。また、なぜカビ臭が発生するのでしょうか。
カビ臭とはどんな臭い?
カビ臭と呼ばれる臭いは、カビの増殖時に生成されるジェオスミンなどの化合物の臭いを指します。
カビの種類や増殖している環境によって臭いは異なりますが、「墨汁のような臭い」「土や泥のような臭い」「腐った木材のような臭い」「絵の具のような臭い」などと表現されることが多いです。
カビ臭の原因
カビ臭の正体は、カビが生成する物質や、カビがエサとなる有機物を分解する際に発生する化学物質の臭いです。実は、カビそのものには臭いがありません。
カビが活発に繁殖することでカビ臭が発生するので、カビを増殖させる環境こそがカビ臭の原因といっていいでしょう。
カビの胞子は人間の居住空間ならどこにでも存在しています。
カビの種類にもよりますが、多くのカビは以下の「温度」「湿度」「栄養源」「風通し」の条件によって増殖します。
- 温度:5~35℃前後の環境で増殖、とくに20~30℃前後の室温で活発化する
- 湿度:湿度が60%を超えると増殖が活発化する。湿度60%以下でも湿ったものや濡れているものの水分を利用してカビは繁殖することもある
- 栄養源:人の髪の毛や皮脂、フケ、食べもののカス、衣類や布団などの繊維(ホコリ)など
- 風通し:風通しが悪い場所ほどカビが増殖しやすい
風通しの悪い場所では臭いもこもりやすいので、カビ臭も強く感じられます。
カビが発生しやすい場所
カビ臭の元となるカビが、発生しやすい場所を紹介します。
浴室

湿度と温度が高く、皮脂や湯アカといったエサとなる栄養分が豊富な浴室は、カビにとって格好の増殖場所です。
とくに、浴槽エプロン(浴槽側面のカバー)があるタイプのバスタブは要注意です。外して掃除をすることが少ない浴槽エプロンの内側は、カビがびっしり増殖していることも少なくありません。
浴槽エプロンの内側で繁殖したカビの胞子が浴室に充満すると、浴室内もカビが生えやすくなり悪循環になりがちです。
エアコン

エアコン内部は、結露とホコリによるカビの増殖が多く見られる場所です。
エアコンを稼働させると、空気を冷却する内部構造と室内の湿って温かい空気が接して結露が生じます。結露の水分と、室内の空気に含まれるホコリを元にカビが増殖することになります。
室内側から見てもエアコン内部の状況はわからないため、カビが増殖していても気づきにくいので注意が必要です。
サッシ

サッシは、冬の結露とホコリによるカビが増殖しやすい場所です。
温かく湿った室内の空気はサッシから伝わる屋外の冷気で冷やされ、結露となってサッシを濡らします。結露の水分と、カビのエサとなるサッシについたホコリや手あか、調理による油汚れなどにより、サッシにカビが増殖するのです。
キッチン

キッチンは、調理の汚れや水回りの水分により、カビの温床となりやすい場所です。
キッチンの食器棚や冷蔵庫などの裏も要注意です。それらの裏に溜まったホコリにカビが発生していることもあります。
また、閉め切ったシンク下の収納スペースも、風通しが悪いためにカビが発生しやすいです。
クローゼット、押し入れ

クローゼットや押し入れもカビが増殖しやすい場所です。
閉め切った状態になるので風通しが悪い上に、溜まったホコリや衣類や布団に付着した皮脂や食べ物のシミなどはカビのエサとなるので、ますますカビが生えやすくなります。
使用していない部屋
普段使用しないために閉め切っている部屋は、湿気がこもりカビが生えやすくなります。とくに、畳は湿気や皮脂、ホコリなどを吸い込むのでカビの温床になりやすいです。
家具の裏
重い家具の裏や、家具で隠れている部分の壁もカビに注意したい場所です。
重い家具は動かす機会が少ないため、カビの栄養となるホコリが溜まりやすいです。さらに、家具の裏は風通しが悪いために湿気も溜まりやすく、カビが繁殖する条件がそろっています。
カビを放置してはいけない理由
カビを放置してはいけない理由は、嫌な臭いが発生するからだけではありません。その他のさまざまな被害を解説します。
健康被害が生じる恐れがある

カビの胞子を吸い込むと、アレルギー反応によって咳や鼻炎を引き起こすことがあります。悪化すると、喘息(ぜんそく)や肺炎になって症状が長引き、肺や呼吸器に深刻なダメージを及ぼします。
また、カビに触れることでアトピー性皮膚炎を発症する人もいるので、カビが付着した衣類や布団にさわったり、素手でカビ掃除をしたりする際には注意が必要です。
カビが増殖する過程で発生する化合物(MVOC)は、臭いが不快なだけでなく、シックハウス症候群の原因になることが分かっています。原因不明の倦怠感や頭痛、めまいなどの症状は、実はカビが原因だった、ということもあるのです。
参考:
作業環境中におけるカビと健康影響(労働安全衛生総合研究所)
シックハウスの新たな問題―微生物由来の揮発性有機化合物;MVOC-(愛知県衛生研究所)
家屋や家財に悪影響を及ぼす可能性がある

放置され増殖したカビが、壁紙や柱、タイルの目地などのシミになり、住まいの美観が損なわれます。
畳や布団に増殖した場合は清掃などである程度のカビの除去が可能ですが、カビアレルギーを発症してしまった場合は、カビに汚染された布団などを廃棄せざるを得ない場合もあるでしょう。
さらに、カビが増殖しやすい、湿度が高く風通しも悪い環境では、木材を腐食させる木材腐朽菌(もくざいふきゅうきん)や木材を食い荒らすシロアリも繁殖しやすくなります。カビが繁殖しやすい状態を放置することで、家屋の安全にも影響を及ぼす恐れがあるのです。
部屋がカビ臭い時の対処法とカビの予防方法
部屋がカビ臭いと感じた時に有効な対処法を紹介します。
これらの方法は、カビを新たに増殖させないための予防法にもなるので、ぜひ参考にしてください。
換気

部屋がカビ臭いと感じた時には、まず換気しましょう。
換気はカビ臭い空気を入れ替えるだけでなく、カビが増殖する原因となる湿気やホコリを含んだ空気を追い出すことができます。
カビを繁殖させないためにも、使っていない部屋やクローゼット、押し入れは、1週間に1回などと決めて定期的に空気を入れ替えましょう。
なお、クローゼットや押し入れにスノコを敷いてから収納すると空気が通りやすくなり、カビが増殖しにくくなります。
また、浴室は温度の高い水蒸気がこもるので、とくに換気が重要な場所です。可能であれば、入浴やシャワーの時だけでなく24時間換気扇はつけたままにするとカビが増殖しにくくなります。
清掃

カビ対策では、清掃でカビ自体を取り除くことも大切です。換気だけではカビ臭の原因となるカビの増殖を止められません。
こまめに掃除をすれば、カビを増殖させるホコリや汚れが溜まらず、カビが生えにくい環境を維持できます。
カビの清掃方法は次の『カビの清掃方法』の章でくわしく紹介します。
除湿する
室内の湿気を除去することも、カビの増殖を抑制するのに効果があります。湿気はカビを増殖させる要因です。
換気でも湿気を追い出すことができますが、梅雨どきなど湿気が多い季節には、エアコンの除湿機能も使うとよいでしょう。
閉め切って使用するクローゼットや押し入れは、定期的に換気をしても湿気がこもりがちです。除湿剤を入れると、余計な湿気を取り除いてくれるのでカビの増殖を抑えるのに効果的です。

出典:紀陽除虫菊株式会社
消臭剤を使用する
換気や清掃を行ってもカビ臭が気になる場合は、消臭剤を使用しましょう。カビの消臭に特化した消臭剤には防カビ成分が配合されている製品もあり、カビを生えにくくする効果も期待できます。
ただし、消臭剤でカビ臭を消したとしても、生えているカビがそのままではカビ臭の根本的な解決にはなりません。また、換気や掃除を怠ると再びカビが増殖することにもなります。消臭剤はあくまでも補助的な利用と考えましょう。

出典:マイレピ
防カビ剤を使用する
カビが増殖しやすい条件が整っている浴室や、あまり使用しない部屋などは、カビ予防のために防カビ剤を併用するのもおすすめです。
置き型タイプやくん煙タイプ、スプレータイプなどさまざまなタイプがあり、使用する場所によっても適した製品があるので、用途に応じて選ぶとよいでしょう。
しかし、防カビ剤は絶対にカビが生えなくなると保証するものではありません。また、その効果は永久的ではなく、効果が切れるとカビは再び繁殖します。
換気や清掃などの基本的なカビ対策を行った上で補助的に使用しましょう。

出典:アース製薬
カビの清掃方法
カビ臭のもとのカビ自体を除去するのに、最も効果的な方法は清掃です。
カビが生えやすい場所ごとに、増殖したカビの清掃方法を紹介します。
なお、どんな場所でも、カビを吸い込んだり直接触れたりしないように換気やマスクや手袋などの装備を忘れずに行ってくださいね。
エアコン
一般の人が自身でエアコンのカビ掃除を行う場合、まず行うべきはフィルターの掃除です。
ホコリ1gには約6万個のカビが存在しているという調査結果※もあります。
ホコリが溜まるフィルターを清潔にすることで、カビそのものだけでなくカビの栄養となるホコリも除去してカビの増殖しにくい環境にすることができます。
フィルターの掃除方法
- 1. エアコンの電源を切る。
- 2. エアコンメーカーの取り扱い説明書に従ってフィルターを取り出し、掃除機でホコリを吸いとる。汚れがひどい場合は中性洗剤を使って優しく洗う。ブラシはフィルターを傷めるおそれがあるので使用しない。
- 3. 完全に乾燥させてからエアコンに取り付ける。
フィルターを清潔に保ちカビを生やさないためには、エアコンを使用する季節には2週間に1回程度の頻度でフィルター掃除をするのが望ましいです。

ファンや熱交換器の清掃はどうする?
最もカビやすい部分なので掃除もこまめにしたいところでですが、熱交換器やファンのカビ掃除は、専門の清掃業者に依頼することをおすすめします。
エアコンでカビが生えやすいのは、室内機の内部にあるファンや熱交換器の部分です。室内の暖かく湿った空気が冷たい熱交換器やファンに触れると結露が生じます。結露の水分とホコリがカビを増殖させるのです。
しかし、熱交換器やファンは精密で壊れやすいため、一般の人が安易に清掃をするのはおすすめできません。さらに、エアコン内部には配線や基盤などの重要部品もあり、DIYの清掃でうっかり水や洗剤をかけると故障する恐れがあります。
クローゼット、押し入れ
クローゼットや押し入れがカビ臭い場合は、中にしまってあるものと、収納場所両方でカビを除去する必要があります。
- 1. 収納してあるものを全て出し、カビが増殖していないか確認する。
- 2. カビている衣類や布団は、衣類などにも使用できるカビ取り剤でカビを取り除く日光に当てて湿気を飛ばすのも効果的。
- 3. 掃除機やブラシなどでホコリを払い、収納場所の清掃がすんでから収納する。

収納してあるものを取り出したら、クローゼットや押し入れの内部も掃除をします。
- 1. 内部に溜まったホコリを、固く絞った雑巾で拭きとる。
- 2. カビが床や内部の壁に繁殖していたら、消毒用エタノールを吹きかけ、雑巾で拭きとる。
- 3. エタノールでもカビが取れない場合は、木材にも使用可能なカビ取り剤を吹きつけて除菌する。
- 4. 内部に風を通し、完全に乾かす。
サッシ
サッシのカビ掃除では、まず増殖しているカビを取り除きます。カビはサッシの表面に繁殖しているだけなので、掃除は比較的容易です。
- 1. サッシの溝に溜まったホコリやカビを雑巾やブラシでかき出して取り除き、雑巾で拭きとる。
- 2. サッシ全体を固く絞った雑巾やウエスで拭きとる。カビが生えていた部分が気になる場合は消毒用エタノールを吹き付けて除菌する。

金属であるサッシが腐食する恐れがあるので、酸性やアルカリ性が強い薬剤を使用するのは控えましょう。
キッチン
キッチンのカビの掃除方法を、部位別に紹介します。
シンクや排水口のカビ除去
- 1. シンクの内側を中性洗剤やクレンザーをつけたスポンジでこすり洗いし、水で洗い流す。
- 2. 排水口のゴミ受けから生ゴミや食べかすを取り除き、スポンジでこすり洗いをする。排水口の内部も同様に洗って汚れを落とす。
- 3. ゴミ受けや封水カップ(下水の臭いが上がってこないためのカップ状の部品)は漂白剤を薄めた液に漬けて除菌する。
- 4. 排水口にも漂白剤を吹き付けて除菌をする。
台所を使えばシンクや排水口が汚れるのは避けられないので、こまめな掃除を心がけましょう。

シンク下の収納
あまり開閉しないシンク下の収納でカビが発生していることもあります。シンク下の掃除方法は、以下です。
- 1. シンク下に収納したものを全て出す。カビが生えている調理器具や食器があったら中性洗剤で洗い流し、必要に応じて薄めた漂白剤で除菌をする。
- 2. シンク下収納の床や壁面の汚れをアルコール消毒液で拭きとる。
なお、シンクの排水が排水管から漏れているためにシンク下にカビが生えていることもあります。その場合は水道修理業者に依頼して補修をしてもらいましょう。
冷蔵庫や食器棚の裏
食器棚や冷蔵庫の裏でカビが増殖していることもあります。目立つカビ汚れがなかったとしても、溜まったホコリは不衛生です。
1年に1回大掃除の時などとタイミングを決めて掃除をすることをおすすめします。
- 1. 食器棚や冷蔵庫をずらし、背面に溜まったホコリを掃除機などで吸いとる。
- 2. アルコール消毒液を含ませた雑巾やウエスで汚れを拭きとる。
- 3. カビが繁殖している箇所は重点的にアルコールを吹き付けて除菌を行う。
- 4. 食器棚や冷蔵庫の背面にある壁もアルコール消毒液で拭きとり掃除をする。
浴室
浴室はカビの生育条件が揃っているので、カビの繁殖を防止するために週1回以上の掃除を行うのが望ましいです。
- 1. 浴室内のシャンプーボトルやいすなどを外に出し、お風呂用洗剤でヌメリや皮脂汚れを洗い落とす。
- 2. 浴槽エプロンが付いているバスタブであれば、メーカーの取り扱い説明書に従ってエプロンを外し、エプロンの内側と浴槽の裏側をお風呂用洗剤でこすり洗いをする。
- 3. 排水口のゴミ受けに髪の毛などが溜まっていたら取り除き、ヌメリやカビを洗い落とす。
- 4. ①で落とせなかったパッキンのカビは、カビ除去剤を吹き付けた後にラップなどで覆ってしばらく置き、洗い流す。1回で落ちない場合は何度か繰り返す。
- 5. 浴室内や取り外した浴槽エプロンを完全に乾燥させたら浴槽エプロンを取り付ける。

浴室に防カビ剤を置くなら、浴室のカビ取りが終わってカビを減らした後が効果的です。
カビ対策は専門家に依頼するのもおすすめ
家の全箇所をきれいにカビ掃除するのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが、専門業者にカビ清掃を依頼する方法です。
カビ清掃のプロに依頼するメリットには以下の点が挙げられます。
掃除をしにくい場所もきれいになる

エアコンの内部やキッチンの排水管、浴室の浴槽エプロンの裏側などは、一般の人には掃除しにくかったり手間がかかったりしますよね。
そんな場所も、プロならカビの取り残しなく、きれいにしてくれます。
たとえば、エアコン内部の清掃は、不注意で水や洗剤をかけるとエアコンを故障させる恐れがありますが、プロなら安心して任せることができます。
掃除をしにくい場所は1年に1回などと頻度を決めて定期的に依頼すれば、掃除がおろそかになりがちな場所もカビを増殖させず清潔な住まいを維持できます。
カビを吸い込む危険がない

カビやカビが放出する化学物質を吸い込んだり触れたりすると、アレルギーなどの健康被害が生じる恐れがあります。マスクや手袋などで防御をしていても、掃除中にカビの胞子を吸い込んだりうっかり触ったりすることもあるので危険です。
プロに依頼すれば、安全に住まいのカビを除去してもらえます。
まとめ
臭いが不快なだけでなく、健康被害を引き起こす恐れがあるカビは、温度や湿気、風通し、養分などの条件が揃うと容易に繁殖します。
カビ臭を取り除き、カビの増殖を抑える方法はいくつかありますが、最も効果的なのは掃除です。場所に応じた掃除をこまめに行い、カビ臭の原因となるカビを除去しましょう。
自分でカビ掃除をやる時間がなかったり、完全に除去できるか不安だったりする場合は、プロのカビ清掃業者に依頼するのもひとつの方法です。
イエコマでは、カビが生えやすく掃除が大変なバスルーム洗浄のサービスをご提供しています。高圧洗浄機を使い、面倒な浴槽エプロン内部のカビもすみずみまで除去いたします。
初めてイエコマのサービスを利用する方なら、バスルーム1室につき8,250円(税込)と、破格の料金でバスルーム洗浄サービスをご利用いただけます。
しつこい浴室のカビにお悩みの方はぜひご検討ください。
バスルーム洗浄ならイエコマ
家の専門家による高圧洗浄機を使ったプロのバスルーム洗浄が…
8,250円/一室(税込)!

エプロン内部の掃除を根元から掃除できていないと、カビが生えて喘息などの健康被害をもたらします!
イエコマが、高圧洗浄機であなたの代わりにエプロンの内部をすみずみまできれいにします